


PlayStation®4用ソフトウェア『Rez Infinite』は、2001年にPlayStation®2で発売された『Rez』をリマスターしたほか、新ステージ「Area X」を含む全編がPlayStation®VR対応となった共感覚(シナスタジア)シューティングゲーム。新時代の共感覚体験を味わった世界中のプレイヤーから絶賛されており、PS VRタイトルの中でも注目を集めているゲームだ。本作の魅力を探るべく、全3回にわたって『Rez Infinite』のスタッフインタビューをお届けする。
第1回は「ゲームシステム」をテーマに、開発会社Monstarsの代表取締役であり、本作ではディベロップメントディレクター兼テクニカルスーパーパイザーの小寺攻氏、ゲームデザインディレクター東郷泰行氏、テクニカルディレクター内田貴規氏、シナスタジア&3Dアーティスト浅地義太氏にお話をうかがった。

『Rez』から15年振りの新作に感じた期待と不安
小寺:自分にとって、『Rez』はとても思い入れのある作品です。今回の『Rez Infinite』の話を最初に聞いたとき、新しく何かすごいことができるんじゃないかという気持ちでいました。とくに、PS VR対応になるということで、以前からVRに向いていると思っていましたし、自分自身がVRでプレイしたいと思っていました。オリジナル版を作った当時からいろいろな実験もしていたので、実現したらきっと面白いものになると期待していました。

小寺攻
(Monstars代表取締役・本作のディベロップメントディレクター兼テクニカルスーパーパイザー)
オリジナル『Rez』でプログラマーを務め、『ルミネス』(PSP®「プレイステーション・ポータブル」用ソフトウェア。2004年発売)ではゲームデザインとメインプログラムを、『Child of Eden』(PlayStation®3用ソフトウェア。2011年発売)でテクニカルディレクターを務める。
東郷:期待していた反面、不安もありましたが、発売前のイベントでユーザーの方にプレイしてもらった際、とても良い感触を得られました。「Metacritic」(世界中のメディアレビュー総合サイト)で数字としても高い評価をもらえたのもとてもうれしく思っています。
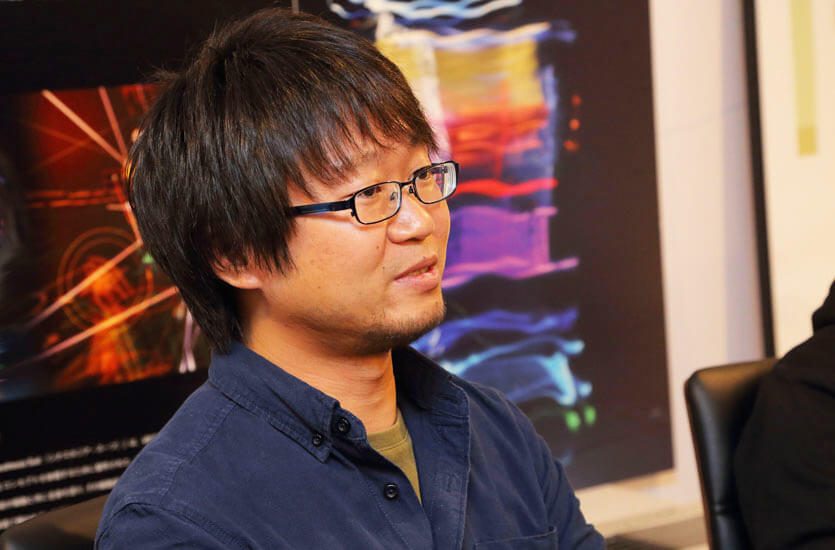
東郷泰行
(Monstarsディレクター・本作のゲームデザインディレクター)
新ステージ「Area X」のステージ設計など、ゲームデザインを担当。
内田:ファンの多いタイトルなので、ユーザーの期待は感じていました。PS VRのローンチタイトルということで、スケジュール的なプレッシャーも大きかったですね。ただ、発売前から外部の方に触れてもらい、良い評価をいただくことが多かったので、自分たちもだんだんと手応えを感じることができました。

内田貴規
(Monstarsチーフテクニカルオフィサー・本作のテクニカルディレクター)
『Child of Eden』でもプログラマーを務め、本作の「Area X」をプログラムする。小寺氏とともに開発全体を統括。
浅地:僕は不安が大きかったですね。作っているうちに本当にこれでいいのかわからなくなって、それでも信じて続けてきました。発売後にSNSで「よかった」「泣いた」というコメントを多くもらえて、それを見て僕は泣きました(笑)。
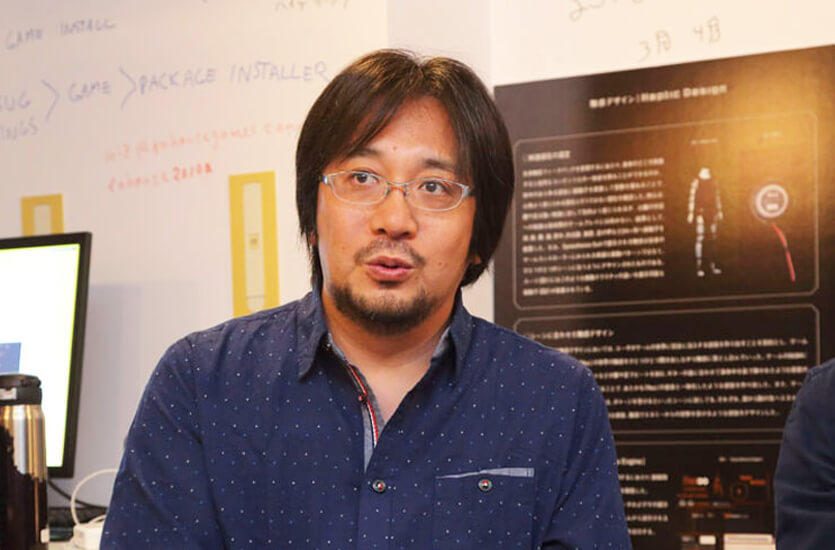
浅地義太
(Monstarsアートディレクター・本作のシナスタジア&3Dアーティスト)
水口氏曰く「シナスタジアの表現に欠かせない人物」。3D表現のほか、振動デザインも担当。
小寺:こうした反応や評価が当然とは言いませんが、スタッフ一同、それぐらいの気持ちで作ってきました。結果的に、予想以上の好評価をいただくことができて、とてもうれしく思います。
気持ちよく楽しめることが開発の原点
小寺:僕たちはこれまで、『Rez』『ルミネス』『Child of Eden』と、水口さんと一緒に共感覚ゲームに取り組んできました。今回の『Rez Infinite』では、リマスター部分のグラフィック強化はもちろん、VRで違和感なく『Rez』を楽しめるという点で進化したと言えると思います。
VR対応の開発では、フレームレートを120に安定させることに注力しました。昔のコードなので、そのまま使うことができず、ひと手間加えなければいけません。VRタイトルだからということもありますが、シューティングゲームとしての気持ちよさを表現するために、120フレームで安定させることは絶対条件だと考えていました。
浅地:不快感は許されないゲームだということは、スタッフもみんな、強く認識して取り組んでいましたね。
東郷:いわゆるVR酔いへの対応も、気をつけて進めました。10〜15人で開発する中で、1人でも不快感を覚えるようなら、すぐに社内共有して調整していました。Monstarsのスタッフの中に特別酔いやすい人間がいまして、彼が不快感なくプレイできるようにすることを一種のバロメーターにしながら、抑えるべきポイントを積み重ねていきました。
小寺:開発を進めていくうちに、不快感の原因というものがいくつかわかってきました。原因が掴めれば数値の調整で改善できるものも多いんです。
内田:オリジナル版のステージのほうが苦労しましたよね。オリジナルのよさを残しつつ、VRで楽しんでもらうことが目的ですが、ボス戦の導入などはダイナミックに視点が変わるので慎重に調整しました。
小寺:開発前に、SIE(ソニー・インタラクティブエンタテインメント)様からVR開発の基本注意点をいただいていたので、まずはそこから着手しつつ、自分たちでコツをつかみ、調整していきました。この注意点は、短く簡潔な言葉で書かれていたので、最初はピンとこない部分もありましたが、あとになって読み返すと、ものすごく大事なことだとわかりました。
東郷:例えば、「地平線を動かさない」や「カメラを奪わない」といった点です。ユーザーが予想しない視点の動きは基本的にはダメですね。『Rez Infinite』ではカメラを奪っていないわけではありませんが、その方法にもコツがあり、奪われたように感じさせない、うまく誘導することが重要でした。
快適に遊ぶためのVRモード難度設計とスタイル選択
東郷:VRモードでArea 1〜5をプレイしてもらううえでは、難しくてストレスを感じるより、多少簡単でも気持ちよくサクサク遊んでほしいと思いました。気づかずに進めた方もいるかと思いますが、ゲームを最初に起動したとき、「VR Style」を「Standard」と「Dynamic」から選択できます。
推奨している「Standard」は、カメラの動きが少なかったり、プレイヤーの攻撃力を高めに調整していたりと、VRで遊ぶ上でストレスを極力軽減して気持ちよく遊んでもらうことを前提にしたスタイルです。
「Dynamic」は、最低限のカメラ調整をしつつ、攻撃力もオリジナルどおりになっていて、VRに慣れて歯応えあるシューティングを楽しみたい方におすすめですね。「VR Style」はオプションの「settings」から変更できるので、どちらも試してみてください。

新ステージArea Xで自由移動が完成するまで
小寺:Area Xの企画初期にあったのは、石原君(石原孝士氏。レゾネア所属。本作のアートディレクター)が描いたコンセプトアートに基づいた、すべてがパーティクル(粒子)で構成された世界を表現するということでした。Area Xはレールライドではなく自由移動でプレイする案が有力でしたが、まだ決定項ではありませんでした。
浅地:開発体制として、オリジナルステージをVR化するチームと、Area Xを開発するチームとが分かれていて、Area X開発は少人数でいろいろ試しながら作っていました。レールライド式であったり、マップはレールライドでもその中を自由に動けたり、そして完全な自由移動まで、サンプルを作ってテストしました。
当然、理想は完全自由移動ですが、パーティクルの世界では対象の遠近感がわかりにくくなるという問題もありました。そんなとき、まだまだ粗い状態のサンプルを水口さんがテストプレイして「おお、気持ちいい!」と言われたんです。ほかのスタッフの反応も同じだったので、やはり一番気持ちいい自由移動でいこうということになりました。
小寺:課題だったのは、制限なく自由に動き回れると、プレイヤーがどこに向かって何をしていいかわからなくなることです。そこで、ある空間サイズに設定したところ、自分がどこにいるかきちんとわかったうえで、気持ちよく動き回れるようになりました。
あとは、プレイヤーナビゲーションの問題。巨大なスネークのような形をしたエネミーが出てきて、プレイヤーに攻撃目標として認識させ、うまく誘導できるようになったことで、「これならいける」という手応えがありました。Area Xはワープしながら最後のボス戦の面まで進んでいきますが、スネークが登場する3面が最初に完成したことになりますね。
Monstarsの独自ツールをUnreal Engine 4へつなぎこむことによって膨大なパーティクル描画を実現
浅地:Area Xの開発では、膨大な量のパーティクル描画も大きな課題でした。当初、ミドルウェアのパーティクルツールを使ってみたのですが、パーティクルを出せる数が足りません。小さいキャラクターを描くには問題ないにしても、空間いっぱいにパーティクルが広がる、石原くんのコンセプトアートを再現するのは無理だろうと思いました。
そこで作り方を変えて、社内ツールをつなぎこんだところ、パーティクルの数を出せるようになったんです。ようやくコンセプトアートを再現できるレベルになり、これならいけそうだという手応えを感じることができました。
内田:ツールをUnreal Engine 4につなぎこんでからは、好きなように、本能のまま作ることができるようになりました。
好きなように作ることは重要で、そうでないと無難なもので終わってしまうんです。これは『Child of Eden』のときに培ったスタンスですね。もちろんみんなと共有しますし、お互いのダメ出しもあります。そういうモノづくりができるところは、この開発チームのよさだと思います。

VRで感覚に訴えることの難しさ
浅地:Area XをVRで表現することの難しさもありました。私は当初、『Child of Eden』で培ったノウハウを元に、音に合わせて派手な光を出そうとしていましたが、周囲から「これでは厳しい」と言われました。これまでの作品のようなイメージで音に合わせて光を出すと、VRでは刺激が強すぎたんですね。それからは、光や音の感じ方には個人差があることを意識して調整しました。
小寺:光の刺激が強すぎると、パーティクルで構成された世界のよさが失われてしまいます。そのバランスの取り方はとても難しかったのですが、これこそがArea XをVRで表現する最大のポイントでもあります。
内田:VRでプレイすると、TVモニターで見るよりも感覚が増幅されたように感じます。開発中、数値をほんのわずかに調整しただけでも変化がわかりますし、数値は変えていないのに、その日の体調や気分によって変わったように感じることもあります。それぐらい繊細なものなので、調整にはかなり時間をかけました。
小寺:VRで感じる刺激はとても繊細なので、開発を毎日続けていると正しい判断ができなくなってきます。私はあえて1週間ほどプレイしない期間を作り、リフレッシュした状態で見るようにすることもありました。ユーザーの方に「気持ちいい体験」という評価をしていただいているので、最後の最後まで慎重に調整を続けた甲斐がありました。
シナスタジアゲームの到達点と未来
浅地:「シナスタジア」を、映像や音など違う感覚がぶつかったときに生まれる新しい感覚ととらえた場合、生まれる感覚の幅や個人の感じ方は無限大です。今回、ユーザーの方がイメージしやすい気持ちよさを提供することが目的でしたが、これでゴールに到達したとは思いませんし、まだまだできることはたくさんあります。今後もいろいろなことを試していきたいと思います。
小寺:社内でいろいろなビジョンを話し合っています。これまで培ってきたノウハウを活かして、みなさんをもっと驚かすことができるような新しいチャレンジをしていきたいです。

第2回は「サウンド/振動」をテーマにお届けします!
◆【PS VR】サウンドとビジュアルの相互作用と融合──『Rez Infinite』インタビュー2<サウンド/振動>
▼PS4®『Rez Infinite』のPS Storeでの購入はこちらから
——————————————
Rez Infinite
・発売元:エンハンス・ゲームズ (Enhance Games)
・フォーマット:PlayStation®4
・ジャンル:共感覚シューティング
・配信日:好評配信中
・価格:ダウンロード版 販売価格 3,400円(税込)
・プレイ人数:1人
・CERO:A(全年齢対象)
※PlayStation®VR対応
——————————————
© 2016 Enhance Games
© 2001 SEGA











コメントの受付は終了しました。